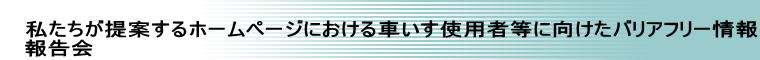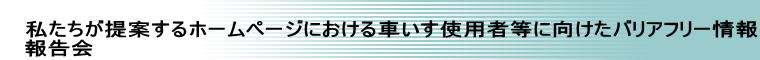|
日 時: 2009年3月28日(土) 13:30〜16:30
会 場: 名古屋都市センター11階 大研修室
年度末のお忙しい時期にも関わらず多くの方が参加して下さいました。ここでは、主に意見交換について掲載します。(参加者:45名)
進行
浅野健
(ひとまちネットワーク東海) |
 |
趣旨と概略
発表者:橋本知佳
(ひとまちネットワーク東海) |
|
ホームページのフォーマットについて
発表者:谷田部勝
(ひとまちネットワーク東海) |
 |
報告会風景
|
13:15〜 受付
13:30〜 開始
あいさつ(趣旨)
1.概略
2.ホームページのフォーマットについて
14:00〜 3.ホームページ試作版体験&意見交換
15:00〜 休憩(20分) ※車いす対応トイレ11階、12階、14階にあります。
15:20〜 4.施設内の案内表示
15:30〜 5.次年度に向けて
15:33〜 6.意見交換
16:23〜 7.連絡、閉会のあいさつ
16:30 終了・後片付け
|
|
18:30〜 交流会 どなんち(名古屋ルーセントタワー2階) (2時間ほど)
|
※(財)名古屋都市センター平成20年度まちづくり活動助成事業
主催:NPO法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海
ホームページ試作版体験
その施設のデータをフォーマットに入力し作成したホームページ試作版を、会場でスクリーンに写し、クリックしながら説明をし、みなさんに見ていただきました。(試作版はWeb上にUPはしていませんが、紙ベースのものは報告書にすべて掲載しています。)
●B駐車場
発表者:川口いづみさん |
 |
●(株)三越名古屋栄店
発表者:鈴木健一さん |
 |
●名古屋ルーセントタワー
発表者:鬼頭弘子
(ひとまちネットワーク東海) |
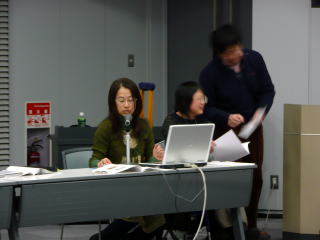 |
●琉球ダイニングどなんち
発表者:田中清之さん(写真中央) |
 |
▲スケジュールに戻る
施設内の案内表示
三越名古屋栄店に提案させていただいた内容を紹介しました。
発表者:鬼頭弘子(ひとまちネットワーク東海)
次年度に向けて
今年度は5つの施設の協力を得て、施設を見学させていただき、どのようなバリアフリー情報(内容、形等)であれば使える、使いやすいものになるか提案できました。次年度からはそれを元に、施設と協働でバリアフリー情報をつくる活動に取組みたいと思います。
ぜひ、一緒に取組んでいただければと考えているのが、ワークショップ等で会場を利用することが多い施設です。車いす使用者等に向けた駐車場やトイレの情報はほとんど出てなく、ワークショップに参加していただいた方からも実際施設を利用した際、困ったという声を聞いています。
▲スケジュールに戻る
意見交換
見学に協力していただいた施設の声
(協力施設):ルーセントタワーは2007年1月に竣工したバリアフリーに配慮された施設です。昨年、見学に来ていただいて、一緒に施設を見学する中でいろいろご意見を伺い、バリアフリーな施設というだけではだめなんだなあと。今年2月に、今回提案された内容の骨子の説明があり、21年度4月以降、予算立てをし、ホームページや施設案内表示の見直しをしたいと考えています。今回作成されたデータをできれば活用させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
(ひとまち):ありがとうございます。こちらこそ、よろしくお願いします。
また、別の施設で伺ったお話では、本店と支店という関係があり、自分たちだけでは決められないのでしばらく時間をいただきたい。ホームページ提案については、改修時の更新のしやすさはどうかといった質問がありました。案内表示提案については、高齢者、ベビーカーを押している方等々にとっても利用できるということで前向きなご意見をいただいています。
◆駐車場について
(A):駐車場スペースで高さ制限しかでていない。車いす使用者用駐車場ということであれば幅はあるということだろうが、長さがわかるとよい。リフトカーは車体自体が長く、リフトを降ろし、車いすの乗降にスペースが必要になる。スロープ付き車両の場合も同様にスペースが必要になる。
(ひとまち):今回は高さ、幅、長さについて、どの情報をだすか検討しました。長さ、幅については寸法は十分あり、バリアフリー施設ということで、高さ制限のみにしました。駐車場の写真を掲載しているので状況は判断できると考えました。
(A):駐車場の出入口に車いす使用者用駐車場がある場合、混雑していて車の出し入れがなかなかできないと思うが、その点はどのようになっているのか?
(ひとまち): 車いす使用者用駐車場と出入口位置関係については、場所(フロア図)で表示しています。係員の有無、係員が配置されていれば対応の内容を記載します。掲載する写真は、駐車場出入口のアップを撮影したものではなく、出入口周辺を入れたものを提案していますので、道路から駐車場(駐車場から道路)へのアクセス状況は判断できると思います。もうひとつ、出入口周辺を入れた理由は、初めてその場所を探すときの手がかりにもなると考えたからです。
(B):駐車場情報は、障害割引の有無だけではなく、利用方法も必要だと思う。母が障害があり、障害割引を利用しようとしたとき、利用方法がわからず右往左往した経験がある。
(ひとまち):障害割引のサービスがあれば、利用方法も記載します。(調査シート参照)
(C):ETC搭載車両について高速道路料金が安くなった。サービスエリアが混雑すれば車いす使用者が利用しにくくなる。そういったバリアフリー情報が必要ではないか。
(ひとまち):どの施設のバリアフリー情報をつくるかは今後検討したい。
◆避難経路について
(C):バリアフリー情報だけではなく避難経路情報が必要ではないか。
(ひとまち):車いす使用者が事前に知っていても実際災害があったとき避難できるだろうか…と考えます。施設側がどのような対応をするか決めておくことが必要ではないでしょうか。
(D):避難経路についてはこちら側が知っていても逃げられない。ましてや初めて出かけた施設では絶対無理でしょう。これは施設側にしっかりやってもらう。何かあったときには誘導してもらう。そのシステムをつくっておくことは大事です。
停電があったとき非常口サインはどうなのか。床に誘導サインが設置してある場合など、電源を落としてみてチェックや訓練が必要ではと思います。
名古屋市で重点整備地区基本構想というのがあって、これまで、名古屋駅、栄、金山、今は大曽根駅周辺をやっています。今日は車いすを対象としているが、そこでは災害等あったとき、どのように知らせるか、誘導するか、聴覚障害の対応について課題となっています。
◆店の対応について
(A):段差等は記載するということだが、段差のある店の前でうろうろしていると、声をかけてくれ介助してくれるがそのような情報はどのように?
(ひとまち):店の対応については、介助、サービスの欄に記載します。
(E):店内のスペース等も関係してくるが、車いすは遠慮してほしいという店もある。車いすの横から料理をサービスしにくい等々あるようだ。
(ひとまち):出かけるときには必需品などあり、車いすが荷物でいっぱいになっている場合もあります。席に着くときは荷物を下ろすなど必要なときもあるでしょう。
◆案内表示について
(F):トイレレイアウト図はどこに設置するとよいか?
(ひとまち):施設内ではトイレ入口。全館フロア案内表示では、多目的トイレ設置階がわかるとよいです。各多目的トイレの入口に、どの階に一般トイレ内で車いすで使用できるトイレが設置されているか、表示されているとよいのではないでしょうか。その施設に何回か出かけているうちに、また時間のあるときなど、一般トイレ内をちょっと覗いてみて、自分で使用できるかどうか確認できる。まったく情報がでていなければ、一般的には、一般トイレ内を見てみることはあまりしません。
福祉施設では1階に設置の全館フロア案内表示に、各階の多目的トイレレイアウト図を表示している施設もあるそうですが、それは商業施設ではなかなか難しいと思います。
詳細情報はホームページにあるとよいです
(F):案内表示提案のところで、避難経路図が目立たないということだったが、消防法で設置しているだけでお客向けではないのでは? 非常口はどこかというぐらいだと思うが、避難経路図を探すということはあるのか?
(ひとまち):施設案内表示が何もなかったということがあり提案しました。避難経路図とフロア案内表示を兼ねている施設もあります。
(F):トイレ入口に設置するレイアウト図に点字をつける場合、設置する高さはどのくらいがよいか?
(ひとまち):車いす使用者向けの情報であれば車いすの高さを考慮してほしい。
(G):車いすと視覚障害と共有できるものもあるが、できないものもあります。視覚障害の場合、立った位置で手を伸ばしたところに案内がないと、どこに案内があるのかわかりません。
中部国際空港ではサインや表示の検討を2年ぐらいやりました。車いすの場合、表示を設置する高さが問題になります。店内の案内表示では、天井からの吊り看板は位置が高くなり勝ちで、見づらくなります。車いす使用者等に向けた情報では、位置、大きさ、個数等が問題になってきますが、店内案内表示と他のサインとの兼ね合いを考える必要があります。
(H):凹凸で便器の位置や形を表示しているところもあります。簡単なピクトグラムぐらいであれば表示は可能と思いますが、手すりのような細かいところまで再現できるかどうか。だから、案内表示のサイズがどのくらいの大きさかとか、凹凸が指で触ってわかるサイズなのかということも考えなくてはいけませんね。
◆スロープの勾配について
(ひとまち):スロープの勾配の表現についてはまだ決まっていません。「きつい」「ゆるやか」という表現は個人差があるので、「12分の1」とか「15分の1」といった数字を使用しようかと考えています。写真についてはスロープを真横から撮影できればわかりやすいが、正面から撮影すると勾配が反映されないので困ったなと。
(E):12分の1とか数字で出してもわからないと思います。それより、長さがどのくらいあってとか、介助について書けばよいのではないでしょうか。
◆提案
(I):ホームページフォーマットの完成度をもう少し高くする必要があると思う。
このフォーマットを使って情報を載せようと思わせる何かが必要。施設側に安心感を与えるツールになるとよい。
フォーマットを利用し施設側だけで情報をつくるということではなく、「この項目で車いすの方が調査し、一定の情報提供のレベルに達しています」と言い切れるものになるとよい。
(ひとまち):この報告書もここまで整理し作成するのにかなり時間がかかりました。しかし、まだ、わかりにくいところがあるということが、この報告会でわかりました。「フォーマット+車いす調査員」という提案。システムについては次年度に向けて取組んでいければと考えます。
(H):必要としている人が必要としている情報にたどり着けるようになるとよい。
事前情報としてホームページ、施設内では案内表示、その中間として「パンフレット」があるとよい。
(J):新しい施設はデザインが優先しわかりづらいところもあります。福祉施設でもわかりづらい設計があったりします。提案するときは、ただ、わからないと言うだけでなく、案内表示であれば、高さや大きさなど具体的な内容を相手に示す必要があると思います。
(G):高齢者では歩くことがしんどくなり、ところどころに休憩できるところがほしくなるんですね。それから、トイレが近くなる。ショッピングセンターが大規模になって、どこにトイレがあるか等、案内表示は大切。
ただバリアフリー情報を載せるのではなく、ホームページのトップページを見て、「行ってみようかな」と思わせるつくりがあるといいなと。
楽しかった、使いやすかった等々、出かけた人のダイレクトな声が気楽に書き込めるところがあるとよい。
(ひとまち):ワークショップでも掲示板の話はちょっと出ましたが、今回は施設側のホームページに情報を載せるということで、管理が必要になる掲示板は提案していません。
◆ワークショップ参加者からひとこと
(K):お手伝いできればと思い参加しました。
(L):豊田の自立生活センターで活動しています。今回、見学は参加できなかったがワークショップに参加しました。金山(ワークショップ会場)に来たことはなく、駅から会場までのアクセスとトイレの場所を確認しました。トイレは緊急に使いたいときがあっても使用中だと使えないので、2〜3ヶ所確認しておきます。
出入口の状況は車いすで入れるか入れないかと大事なことですが、このワークショップで、車いす使用者はみな同じではなく、一人ひとり違うということに改めて気がつきました。電動車いすと言っても違いがある。人によって便座へのアプローチが右側からだったり左側からだったりと異なるし、スイッチ類の設置されている位置、高さや種類については、自分は腕が上がらないので、洗浄スイッチが高いと使えません。だから、手をかざすタイプのセンサー式の場合は、使えない。自分の場合はボタン式がよいが、ボタンを押しづらい人もいる。
ワークショップで行った活動を豊田でも広げていきたいと思いました。
(ひとまち):お互い活動したことを意見交換し、今後の活動に活かしていけるとよいですね。
(M):頭でわかっていても建物ができて実際を見て「えっ」と驚くことがあります。障害のある当事者の視点を勉強できればと思い参加しました。個々の障害によって個別性を強く感じた。個別性があっても、それぞれの人が使いやすいという回答があるのではないかと。ワークショップに参加して、これまで気がつかなかったことを気づくことができた。
今後に向けては、施設に対してはやはり利用する当事者が声を出していくこと、わたしたちはそれをサポートする立場かなと。
今回は名古屋市で取組み、今、豊田での話があり、愛知県へと、当事者が手を挙げて、この活動が広がっていくのではないかと期待しています。
(ひとまち):使える情報をつくるということが目的ですが、情報を協働でつくるということも目的です。また、これにはこのような目的が、このような事情があります等々、施設側の話を聞くことができれば、それに対応できます。施設側からは、施設の使い勝手についての質問があれば答えることができ、情報の内容、提供の仕方についても一緒に考えることができます。設計の方が参加していれば、次の施設の設計に活かしていただけるのではないかと期待します。
(N):一人歩きをしています。点字ブロックが設置してあっても、その情報がない。地下鉄構内は点字ブロックが設置してあるが、地上に上がるとない。
もっと出かけたいと思うが、情報がないと利用できません。視覚障害の情報をつくっていこうと、いろいろな人に話して、やっと一緒に活動するグループも見つかり、これから踏み出そうというところです。
一度、このワークショップに参加して、細かいところまでやっているんだと勉強になった。
(ひとまち):車いすは、外から見える障害で当事者以外の人にも理解しやすい。視覚、聴覚については、どんな情報が役に立つのか、どのような表現がよいのか、提示していただけるとわたしたちも勉強になります。
(O):20年近く福祉施設の建築設計をやっています。最近は高齢者の施設。昔と比べると手すりの設置高さも違ってきている。だんだん使いやすい寸法になってきているんですね。使いやすい寸法を勉強したい。
地元の県で福祉のまちづくり会議等に参加し、いろいろ意見をだしたが、提案しておわりなんですね。提案して対応があるということが大事で、ルーセントでは対応があるということですばらしいなと思いました。
仕事柄ハードが中心になるが、ハードとソフトのバランスが必要なんだと。先ほどコメントされた視覚障害の方と帰りが一緒になり、どのように誘導するのかわからなかったが「肩を貸して」と言われ、初めて知った。
障害のあるなしに関わらず、まちに出かけて行けるようになるとよいと思います。今後も、この活動に協力していきたいと思います。
(P):山間部の地域です。バリアのある地域にいる人たちが、もう少しこういったものが利用できないかと思い参加しました。なかなか現実は難しいところがあります。
(ひとまち):予定の時間を過ぎていますので、このあたりで報告会は終了させていただきたいと思います。本日は、みなさん、お忙しいところご参加下さいまして、ありがとうございました。今後とも、よろしくお願いします。
▲スケジュールに戻る
(文責:橋本知佳)
▲ページの先頭に戻る
|