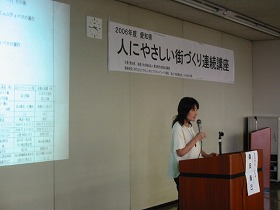「誰もが、いつでも、どこへでも 「誰もが、いつでも、どこへでも
〜障害者・高齢者の地域生活における移動のバリアフリー〜」
講師:水谷克博さん(NPO法人東海福祉移動研究協議会
常務理事)→こちら
 「"公共交通の危機"と交通権」 「"公共交通の危機"と交通権」
講師:森田優己さん(桜花学園大学 人文学部観光文化学科 教授)→こちら
 グループの時間→こちら グループの時間→こちら
|
 13:05 講義「誰もが、いつでも、どこへでも 13:05 講義「誰もが、いつでも、どこへでも
〜障害者・高齢者の地域生活における移動のバリアフリー〜」
講師:水谷克博さん(NPO法人東海福祉移動研究協議会
常務理事)

1.障害と街づくり
・
年を取れば誰でも体力は落ちてくる。事故に遭ったり病気になるなどして障害を持つようになることは誰にでも起きる可能性があるが、自分には関係のないことと考えている人たちは多くいる。
・
車いす体験で気づいてもらえたと思うが、エレベーターやノンステップバスがなければ地域で満足した生活はできない。
・
今、自分が車いすを利用する立場になったと想定して、家から外出するときのことを考えてみて欲しい。まず家から道路まで出られるか。アクセス方法はどうか。会場まで来ることはできるか。
2.現在の公共交通機関の状況と対応
・
名古屋市交通局は5年前、今後、導入するバスはノンステップバスにすると宣言した。
・
名古屋市は最大約1600台のバスを保有していた時期もあったが、地下鉄の建設が進んだこともあり、今保有している約1200台のバスを約800台に減らす方針。
・
エレベーターがない地下鉄駅は9ヶ所ある。エレベーターはあっても、よそのビルのエレベーターを借りているところでは稼働時間が決まっており、始発から終電まで利用できない。
・
東山線名古屋駅は今年10月から駅前の新しいビルのエレベーターを利用できることになり、始発から終電まで利用できることになった。
・
名鉄は人件費削減のため、無人駅がある。車いすの場合、前日18時までに乗車・降車駅、時刻等を連絡しなければいけない。
・
JRは、多目的ルームの予約は駅長室に行き、申し込まなければならない。
・
JR東海は、これまでハンドル式車いす(セニアカー)での乗車は拒否していたが条件付きでOKになった。しかし、いまだに事実上拒否は続いている。
3.STS(※)とそれを取り巻く問題
・ 私は養護学校卒業後は通勤困難等で長期間在宅の生活が続いた。
・ STSの対象者は"多くはない"、しかし、それを"必要としている人たち"にどのようにサービス体制をつくっていくか。
・
1997年より障害当事者団体「せと車いすセンター」で福祉車両を利用した車いす利用者の外出支援事業部事務局に関わる。
・
福祉車両は1台500万円(ハイエースなど)と高額である。
・
寄贈する側としては、信用がないとして、ボランティアや障害者団体に贈る場合はリスクがあるが、日本財団など贈り続けた。
・
補助をもらっても、障害者団体では少額で運転手一人確保するぐらいがせいいっぱい。例えばリフト付き車両で10年間に3000キロのみの運行では、会員が少なく有償運送を行わない運行では保険や車検など維持費が負担になり廃車。運転者の確保や運転者の日程調整などコーディネートが大変。
・
2000年2月に障害当事者団体とNPO等ボランティア団体の協働と共生を目指し「愛知県ハンディキャブ連絡会」を結成。(現在、様々な理由から活動休止)
・
行政からのサポートはこれまでほとんどなかった。同じ内容でも業者に委託する場合は高額な費用を支払っている。私たちは安い労働力と見られる。
・
2000年介護保険制度が始まり、これまで車いす利用者の乗車拒否などしてきたタクシー会社の参入。
・
2006年6月、道路運送法改正。"有償"と"無償"、"事業者"と"NPO法人"
・
ドア・ツゥ・ドアではなくベッド・ツゥ・ベッドがSTSの役割と考え、今後は重症患者送迎と救急搬送への取り組みへ。
STS(スペシャル トランスポート
サービス)
バスや電車など公共交通機関を利用できない高齢者や障害者など移動制約者のために便宜を図る交通サービス
 14:45 講義「"公共交通の危機"と交通権」 14:45 講義「"公共交通の危機"と交通権」
講師:森田優己さん(桜花学園大学 人文学部観光文化学科 教授
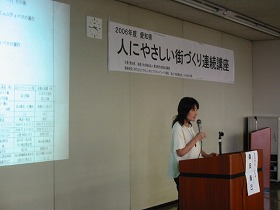
1. はじめに 「明日は我が身の発想を」
・
交通困難者→車いす利用者、高齢者、妊婦さん、一時的にけがをした人など→車を利用する(自ら運転、他者が運転)
・
100歳になっても安心して運転のできる車
・ 車をもっとバリアフリーなモノへ
2. 車の使い方を考えよう
名古屋交通戦略
・
スリッパ感覚で車を利用→車から公共交通利用へ→交通渋滞の解消、環境へ配慮
・
運転する人では半数の人が人身事故を起こし、150人に1人が死亡事故を起こしている。
・ 利用したい公共交通へ→お得なチケット販売など
・
シームレス(継ぎ目のない)な公共交通へ→誰でもいつでもどこへでも行けること

3. 現状では公共交通の路線そのものがなくなっている
・ モータリゼーションの進展と規制緩和
・
2000年以降、続々と進む地方鉄道の廃止
・
日本の各地で日々、路線バスの休廃止や県による補助金打ち切り問題が報じられている状況→公営、民営問わず乗り合いバスの7割が赤字、廃止申請へ。
・
ついに、新交通システム(桃花台)も・・・
・ 車への過度の依存の一層の広がり→小型車保有が増えている
・
高齢者ドライバーの増加にともない、高齢者の死者数は10年前に比べ1.2倍以上
4.「動き始めた市民たち(2004年度のひとまち講座のテーマ)」その後
・ 高齢者の運動による公共交通空白地域でのコミュニティバスの運行
・
NPO等によるコミュニティバスの運行
・ 行政が主体となった鉄道の存続とコミュニテイバスの運行
・
国による「交通と福祉の統合的交通政策」の実施?
ボランティア輸送の制度化
<これまでになかった動きと課題>
・
陳上型から「街づくり」のひとつとして提案する。
・ 行政、事業者任せをやめ、自分たちで考える。
・ 自治基盤として考える。
・
住民、行政、事業者の協働による取り組みがでてきたが、存続できる保障はない。
5. 交通は生きる権利を保障するために必要不可欠なもの
・
「交通権」→市民の交通する権利。フランスでは国の責務で行うモノと社会権として明記されている。
・ 交通問題は公共交通機関問題にあらず。
・
生きる権利の危機としての公共交通の危機。→買い物、施設利用のための移動、通勤・・・
・
地方自治や国のあり方の問題としての交通問題。→ドイツでは多額な補助費が当てられている。日本は地方交付税がだんだん減らされている・・・
6. おわりに
発展途上の「協働」と「賢い市民」の育成が必要
 16:15 グループの時間 16:15 グループの時間

|