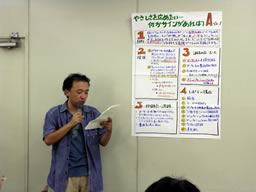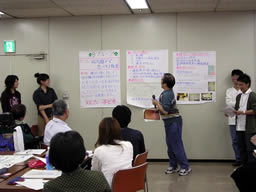トップページ>講座>愛知県 人にやさしい街づくり連続講座>2005年度 私らしくまちで暮らす>第9回
2005年度 私らしくまちで暮らす
|
第9回 【グループワークの中間発表】 |
|
日時:10月1日(土)13:00〜17:00
会場:愛知県社会福祉会館 3階 ボランティア学習室
第9回 【グループワークの中間発表】
グループレポートの中間発表をしよう
今後の活動計画を考えよう |
グループワークが始まって2週間が経ちました。今回は、グループワーク進捗状況や今後の活動予定を模造紙を使って各グループは発表します。そして、コメンテーターの方の意見などいただき、各グループは残りの2週間をグループレポート発表会に向けグループワークします。 |
|
13:00 はじまり
13:10 【ステップ1】グループレポートの中間発表をしよう
15:10 <休 憩>
15:20 【ステップ2】今後の活動計画を考えよう
16:25 今後の活動方針を発表しよう
16:40 次回の連絡&後片づけ
各グループ中間発表
<全体で>
・ 1グループ5分で、グループレポートの中間発表(テーマ、レポートの構成、調査過程、調査結果、
結論の方向性、進捗度、問題点など)を行います。
・ ポストイットにコメントを書き、他グループが発表した模造紙に貼り付けていきます。
・
ポストイットに書かれたコメントの内容を確認しながら、疑問や意見に対する回答を検討します。
|
|
Aグループ
テーマ:やさしさを広めたい
健常者・障害者に関わらず、手助けを求めたい側、手助けしたい側が共にどう接すればいいのかわからず、お互いに躊躇しているのではないかという議論となり、何か簡単な意思表示(サイン)をすることにより、助けやすい、助けを求めやすい、または声を掛けやすい、掛けられやすい社会になるのではないかと考えた。
- アンケート数は300あれば、解析できる数値ではないかと設定
- サインのツール:ステッカー、ストラップ、赤い羽根、バッジ、キーホルダーなど考えている
- 普及についてどうするか検討
- アンケートは始めている→講座受講者、障害当事者団体は実施。今後は、知り合いや外に出て集めたい
|
|
|
Bグループ
テーマ:双六遊びで思いやり教育
障害のある人について分け隔てなく、行動できる事が大事。
子どもたちに、やさしさについて考えるきっかけづくりを提案したい。
- ・双六を選んだ理由→スタートとゴールがあり、疑似体験やクイズを取り入れて、遊びを通じて考えてもらえるものをつくりたい
- こどもを対象にしたのは、成長していく時期に「知る」という過程で障害について考えてもらう場をつくりたい
- 双六の中で使ったことばについて、なぜ使ったか理由を入れたい
- 調査結果:(表)→子ども、高齢者、外国人、妊婦、一般の方、それぞれの立場で困っていることをグループで話し合ってまとめた
- 双六の活用法の検討をする
- 場面想定の補足→いろいろな人に聞き取りしたい
|
|
|
Cグループ
テーマ:いつかくる日を自分らしく生きるために!
誰もにいつか必ずくる高齢者の生活、明日はわが身(今の社会では、いつ事故や事件に遭遇するかわからない)→障がいをもった生活。障がいをもった(高齢になったら)自分が自分らしく生きるためにどうするべきか考える。
- 視覚障害や聴覚障害があるが、講座で車いす体験をしているので、対象は車いす利用者とした
- 車いすで、実際、自分の家から外出できるかどうか、公共交通機関が利用できるかどうか検証する
- 中途で車いすでの生活になった方もヒアリングしたい
- Iさんは車いすユーザー。あまり実家に帰っていない。今回、実家に帰ってみる→親孝行できる?
- 補助金制度等も調べている
- 住宅リフォームは実施前・後と取り上げたい
- 結論の方向性は??? 全体の進捗度は20〜30%
|
|
|
Dグループ
テーマ:精神障害を知っていますか? 〜地域と共に生きるために〜
目に見えない障害をもつ人たちが地域で差別なく、みんなと同じように生活できるようになるためにはどうしたらよいか。ホットスペースの提案。
- 現在、精神障害のある方たちが生活しているスペースではどのようなものがあるか4箇所調べた。
- ほっとする場所が身近にたくさん欲しい→くれよんBOXは昭和区にある、遠くに住む人はなかなか来れない。クニハウスは千種区にある。
- 精神障害は規則正しい生活をしていない人がかかりやすいとか、生活習慣病の行き着く先であるといったような偏見があったりする。実際に精神障害になりやすいのはどのような人か、なった場合どうするか等、客観的にデータを調べる。統計的には100人に1人は精神障害にかかっていると言われている。精神障害ということばもよいとは思わないが。
- ホットスペースの開拓
- パンフレット作成・配布
|
|
|
Eグループ
テーマ:困ってる人って誰? 〜情報交流の場作り〜
車いす体験して実際「困った」。車いすの人は困っているんだというイメージになったが、身近のKさんに聴いたところ、「困っていない」という返事。なぜ、困っていないかアンケートをした。その結果、情報をとても多く持っていることがわかった。その情報をみんなにどのように広く提供できるかということで、「情報交流の場作り」を考えたい。
- 調査結果では、経済的理由、豊富な情報源、車が運転できるなどの現存能力があることがわかったが、「情報源」に着目することにした。
- 理想のホームページ作成(困りごとを解決するための情報の所在が分からない人のために、地域に存する解決に役立つ情報を容易に取り出せる場づくり)
|
|
|
高田弘子さんコメント
<全体>
・
いきなり発表するのではなく、まずは、自己紹介(講座で車いす体験をした等、講師にわかるように)をすること
・
会場の様子(聴いてもらえる状態かどうか)を見ながら話すこと
・ 他のグループはどうかということを気に掛けること
・
使うことばは、よく検討する必要がある
・
「発表会」では聴いてもらう人のことを念頭に置き話す
・ 対象としている「地域」を限定しないと提案に結びつかないのではないか。具体的な地域を設定してほしい
|
今後の活動計画を考えよう
<グループで>
・ステップ1のコメント等を踏まえ、活用する部分や軌道修正する部分等を議論し、今後の活動計画を練ります。
今後の活動方針を発表しよう
・ 1グループ2分で、ステップ2の決まった結果や今後の活動計画を発表します。
・
コメンテーターの高田弘子さんから各グループごとにコメントをいただきます。
コメンテーターからのコメント
Aグループへコメント
- サインということばがよくでてくるが、いろいろな意味に取れるので明確にすること
- 「私は聴覚障害者です」ということを表すマークを付けるのは嫌ではないか
- 「サイン」を通して行動を起こすこと、行動に移すことが必要で、「サポートしたいけどなかなかできないという予備軍」が「サイン」で「サポーター」に変わるきっかけになるのではないか
- 根拠の説明が必要
- 口頭では、発表項目の順序によって、相手の気を引きつけておくことが左右される
- 「ツールの検討」は前の方に持ってくる
Bグループへコメント
- 双六が完成してからコメントしたいが・・・
- 障害のある子もない子も一緒に遊べるとよい
- 疑似体験については、紙上で疑似体験できるものが「防災」をテーマにしたものである。それを取り入れてはどうか。
- 「双六をしたい!」という気持ちを持ってもらうのはどうするのか
- 「スタート」と「ゴール」をどうするのかが、とても大切
- 双六の物語性が重要→受講者回答:考えている
Cグループへコメント
- 「多かった」という表現ではなく、具体的な数を示すこと
- 相手にわかるようにことばを適切に選んで書くこと
- 「施設や家を改善することが、なぜ自分らしく生きることに繋がるのか」というポストイットがあった。ポストイットに書いてあることがわからなければ、相手に聞きに行くこと。また、当事者ではないのなら、聞きに行くこと。そうしないと社会は変わらない。
- いろいろ書いてあるが生活感がない
- Iさんをメインに計画を立ててはどうか
- 高齢者体験をして欲しい
Dグループへコメント
- 「精神障害」を取り上げているが、これは知識がもっといる
- テーマが難しいので、自分たちができるテーマに
- ノーマライゼーションが求められ、心のバリアがあるということなら、「ホットスペースをつくろう」をテーマにした方がよい
- 当事者のヒアリングだけではなく、自分たちの地域に持ってきませんかという調査はしたか?
- 調査内容を明確にして欲しい
→くれよんBOXは、地域とどのような繋がりがあるのか、活動内容など
- 行政への提案よりも、直接行動(例えば、図書館にスペースを!)は、現実的だしすぐできる。当事者にとっては早くそういった場が欲しいはず。
- ホットスペースの例が貧困 もっとたくさんあるはず 公民館、学校等々
Eグループへコメント
- 発表会までにHPを立ち上げてください→欠点がわかる
- Aグループとやっていることは同じなので、連携したらどうか? 知らなかったのかな?→受講者回答:知らなかった
- 自分たちの持っている情報は少ないと思ってやって欲しい
- 他のグループの情報も載せるとよい
- 項目には、なぜ、必要なのか理由を明記してあるとよい
- HPアクセスできない人もいる。この方法が使えない場合はパンフレットへというように、2〜3考えておくこと
|