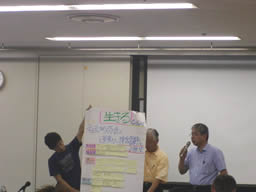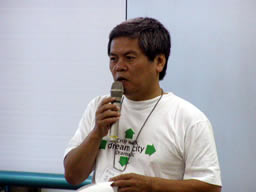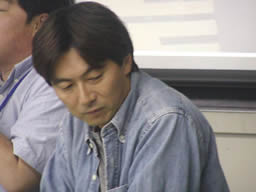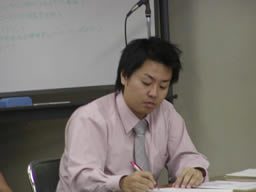トップページ>講座>愛知県 人にやさしい街づくり連続講座>2005年度 私らしくまちで暮らす>第7回
2005年度 私らしくまちで暮らす
|
第7回【制度学習と、人にやさしいまちづくりの広がり
・その2】 |
|
日時:9月10日(土)10:00〜16:00
会場:産業貿易館西館9階 第3会議室
第7回【制度学習と、人にやさしいまちづくりの広がり・その2】
各グループ発表
講義 「人にやさしい街づくり条例と交通バリアフリー法・ハートビル法」
日比野好幸(愛知県建設部建築指導課)
シンポジウム 第3部「協働」多様な協働のスタイルの試み
コーディネーター:
小寺岸子NPO法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海)
シンポジスト:
山口良行さん(わだちコンピュータハウス調査企画部)
尾崎由利子さん((株)コムデザイン)
馬久地
浩さん(岐阜経済大学地域連携推進センターチーフコーディネーター)
富永和久さん(半田市役所) |
今回で「知る・学ぶ」は終わりです。これまで、「居住」「交通」「社会保障の歴史」について学んできました。その上で、午前の講義では、人にやさしい街づくりの根本にある制度について、また、午後は、シンポジウム形式で、行政主導だけではなく、多様な協働のスタイルの試みに学びます。テーマは「協働」です。 |
 |
|
10:00 講義 「人にやさしい街づくり条例と交通バリアフリー法・ハートビル法」
日比野好幸(ひびのよしゆき)(愛知県建設部建築指導課)
※講義が始まる前に、5グループが先回のグループ討議の内容を発表しました。(下の写真)
|
11:30 終了
12:00 昼食
13:00 再開、本日の流れについて説明
13:10 シンポジウム 第3部「協働」多様な協働のスタイルの試み〔公開講座〕
コーディネーター:
小寺岸子(こてらきしこ)(NPO法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海)
シンポジスト:
山口良行(やまぐちよしゆき)さん(わだちコンピュータハウス調査企画部)
尾崎由利子(おざきゆりこ)さん((株)コムデザイン)
馬久地
浩(めくちひろし)さん(岐阜経済大学地域連携推進センターチーフコーディネーター)
富永和久(とみながかずひさ)さん(半田市役所)
15:15 <休憩>
15:25 質疑応答(会場から)
15:40 まとめ(シンポジストからキーワード)
15:50 次回の連絡&後片づけ
16:00 終了
|
各グループ発表
講義 「人にやさしい街づくり条例と交通バリアフリー法・ハートビル法」
日比野好幸(ひびのよしゆき)(愛知県建設部建築指導課) |
|
|
|
・条例の制定から改正までの流れについて
・交通バリアフリー法とハートビル法について、また、国の方で、このふたつを合わせる流れ(新法になるのか、それぞれの改正なのかはまだ不明)があるのでその点について
・昨年ぐらいから国の方ででてきている新しい施策について
以上、3点についてお話がありました。 |
シンポジウム 第3部「協働」多様な協働のスタイルの試み〔公開講座〕
コーディネーター:
小寺岸子(こてらきしこ)(NPO法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海)
シンポジスト:
山口良行(やまぐちよしゆき)さん(わだちコンピュータハウス調査企画部)
尾崎由利子(おざきゆりこ)さん((株)コムデザイン)
馬久地
浩(めくちひろし)さん(岐阜経済大学地域連携推進センターチーフコーディネーター)
富永和久(とみながかずひさ)さん(半田市役所) |
|
|
|
★山口さんには「当事者と企業」、富永さんには「地域と行政」、尾崎さんには「コンサルタントと行政」、馬久地さんには「地域と大学」という立場で、お話しをしていただきました。
|
|
|
|
コーディネーター 小寺岸子 |
|
1)
山口良行さんのお話
■中部国際空港ユニバーサルデザイン研究会の障害当事者の立場からの取り組み
- 中部国際空港の計画が決まったとき、せっかくつくるのであれば、障害者・高齢者に使いやすいものをつくって欲しいと要望した。仕事として責任を持ってやりたいと、何度も足を運び、私たち障害当事者の声を空港の設計に取り入れてもらえることとなった。2000年中部国際空港ユニバーサルデザイン研究会が発足。
- ユニバーサル・デザインの視点。様々な障害の方に参加してもらい、たくさんの意見を集め調整し、報告書にまとめ提案した。
- 障害別に分化会を設置し運営していった。提案は建築の法律が壁になることもあった。こちら側のチェックが済むまで、空港会社では工事を中断して待っていてくれた。提案がすべて通ったわけではなく、また、ソフト面では私たちの提案が通らなかったこともあった。
- 中部国際空港で得た経験を、今後は、新設・既存の空港や駅、公共施設の改修に活かしたい。
|
|
|
|
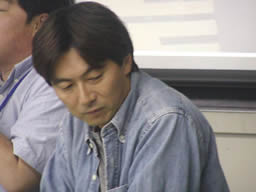
|
|
2)富永和久さんのお話
■半田市の人にやさしい街づくりの事例から
- 平成11年度に半田市人にやさしい街づくり基本計画が策定された。ハード・ソフト、市民の方にどのように理解してもらうかということで、そのひとつにWS方式で進めていくことが書かれている。
- 半田市を5つの地域に分け、自分の住んでいる地域について、人にやさしい街とはどのようなものか、人にやさしい街をつくるにはどのようにしたらよいかを考えてもらおうと始めた。社会福祉協議会、日本福祉大学、ひとまちアドバイザーの方たちに参加してもらい企画計画した。はじめは公募しても人が集まらず、まず、人にやさしい街づくりを知ってもらうことにした。
- 車いす体験して街を点検し報告書を作成、市役所・鉄道・電力会社などに持っていき改善要望した。
- 行政と市民のワークショップの成果として、当事者参加で既存の公民館にスロープがついた。WSの会場にしてきた場所がバリアフリーでなかったこと、そこから市民の意見とやる気が出てきて、WS後、参加メンバーの一人が半田工業高校の生徒さんと知り合いで声を掛け、スロープを手作りした。
- バリアフリーを進めていくには、いろいろな課との連携が必要である。若手は参加してくれるが、年のいっている人は参加したがらない。市民にも、もっと人にやさしい街づくりについて関心を持ってもらいたい。いろいろな工夫が必要と感じている。今後は、行政の役割は、NPOや市民団体のサポートと思っている。
|
|
3)尾崎由利子さんのお話
■福祉コンサルタントの仕事
- パソコンでアンケートの集計や分析の仕事をしていた。市役所から、福祉機器の施策をつくる委員会を始めるが手伝って欲しいと言われ、それが福祉コンサルタントのはじまりかと思う。
- 愛知県の市町村で、人にやさしい街づくりの施策をつくる手伝いをするようになった。10年ぐらい前になるが、津具村の障害のある人100人に「何に困っている」「何がしたい」かと一軒ずつヒアリングした。子育て支援の計画策定を手伝うことになったときは、学童保育や休日保育をやっているところや、大学の先生に聞きに行った。調査し集計して報告する、一つ間違えると大変なことになるので、集計はきっちりやる必要があると思い、友だちと会社((株)コム・デザイン)をつくり仕事を始めた。
- コンサルタントは行政と市民が協働して仕事ができるようにお膳立てをする仕事だと思う。
- 協働で大切なことは、対等の立場、目的に向かうこと、隠し事をしないこと、行政―住民、それぞれの性質を尊重した活動をすること。
- 行政は情報はだしてきちんと説明する必要がある。行政はすぐには動き出せない。できないことはできないということが大事。今はまだお金のある時代だからよいが、今後、どうして行くか今以上の協働が必要になるでしょう。
|
|
|
|
|
|
4)馬久地浩さんのお話
■大垣マイスター倶楽部の事例から
- 1998年に発足。全国に先駆けて郊外の大学のゼミがJR大垣駅南口の中心市街地の店舗を借りて、研究室を構え、まちづくり活動を実施。大垣地域産業振興センターと大垣商店街振興組合と岐阜経済大学の共同研究室として運営されている。
- 2003年地域連携推進センターが設立され、地域経済研究所の一機関としてマイスター倶楽部は位置づけられ調査研究費がでるようになった。それまでは、助成金を申請し運営にあてていた。現在、活動グループは10ある。
- 協働では、情報の公開と共有、協働関係の仕組みづくり、市民と行政の意識改革が必要である。
- バリアフリー調査研究グループでの取り組みのひとつに、学生が教える立場になって、小中高等学校との連携事業「総合学習でバリアフリー体験学習」などいろいろな立場の人と活動を実施し横の繋がりをつくってきた。駅前から商店街へ、その他の地域へ活動は広がっている。
- まちづくりの基本は危機感だと思う。安心・安全のまちづくりを目指して、防犯ネットワークづくりをしており、新しいネットワークをつくることで新たな発見に繋げていきたい。難しいテーマなので学生自身の問題としてどのように取り組ませるかが課題。
|
|
★ シンポジウムのおしまいに、各シンポジストから、今日のキーワードをだしていただきました。
山口良行さん <当事者が主役>
富永和久さん <ネットワーク>
尾崎由利子さん <楽しくお金をかけずに、次世代へ>
馬久地
浩さん <仕掛けづくり> |
|