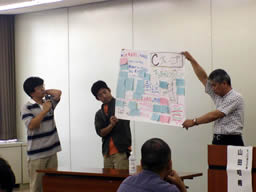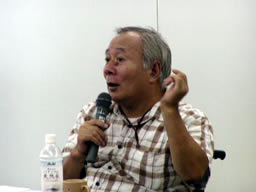�g�b�v�y�[�W���u�������m���@�l�ɂ₳�����X�Â���A���u����2005�N�x�@���炵���܂��ŕ�炷����6��
2005�N�x�@���炵���܂��ŕ�炷
|
���U���@�@�y������z |
|
�����F9��3���i�y�j13:00�`17:00
���F���m���Љ����قR�K�{�����e�B�A�w�K��
��U��y������z
�e�O���[�v���\
�u�`�@�Љ�I��҂Ɖ^���\��Q�҉^���̗��j�\
�R�c���`�i��܂������悵�j����i�Љ���@�l�`�i�t�����̉Ɓj
����@���ی����x
�����錩�i�Ȃ��ނ炠���݁j����i�����Љ���m���k���j
�O���[�v���c |
�@����́u�m��E�w�ԁv�̂S��ځB��U��̃e�[�}�́u������v�B��Q�҉^���̗��j�Ɖ��ی����x�̌������ɂ��Ċw�т܂��B |
 |
|
�P�R�F�O�O�@�͂��܂�
�S�O���[�v�����̃O���[�v���c�̓��e�\���܂����B�i���̎ʐ^�j
|
�P�R�F�P�O�@�u�`�@�Љ�I��҂Ɖ^���\��Q�҉^���̗��j�\
�@�@
�R�c���`�i��܂������悵�j����i�Љ���@�l�`�i�t�����̉Ɓj
�P�S�F�S�O�@����@���ی����x
�@�@
�����錩�i�Ȃ��ނ炠���݁j����i�����Љ���m���k���j
�P�T�F�P�O�@���x�e���@
�P�T�F�Q�O�@�O���[�v���c
�@
�e�O���[�v�ŁA�����̍u�`�Ǝ�������ƂɃf�B�X�J�b�V�������܂��B
�P�U�F�S�O�@����̘A������ЂÂ�
�P�U�F�T�O�@�I��
|
�e�O���[�v���\
|
�`�O���[�v
�E���܂������ʋ@�ւ��g���Ă��Ȃ����Ƃ���������
�E���͂ňړ��ł��邱�Ƃ���ʂ̌����ƌ�����
�E�n������̊����ɂ��āA�����͂ǂ̂��炢�ł��邩�Ƃ������Ƃ�b��������
�@
���ӔC������̂ŁA�{�����e�B�A�Ƃ��Ă͂Ȃ��Ȃ����Ȃ�
�E�m�o�n�Ԃ̃l�b�g���[�N�A���������K�v |
�b�O���[�v
�E������ʋ@�ւ͗��p����̂ɕs�ց��g���ɂ����Ƃ���͐��ɂ���
�E�n�[�h�E�\�t�g�A���Ƀn�[�g�̕������K�v |
|
|
�c�O���[�v
�E������ʋ@�ցA�ԂƂ���A�����⊮������̂Ƃ��ẴX�y�V�����E�g�����X�|�[�g�i�m�o�n�̃T�|�[�g�j
�E�}���قƓ����l�����Ō�����ʂ����p�҂�������ΐŋ��Ŏx���Ă��悢�̂ł͂Ȃ���
�E�ڑ��T�[�r�X���{�����e�B�A�ł��Ă����̂͂ƂĂ���ρB�܂��A�{�����e�B�A�Ƃ͉����낤�ƂȂ����B |
�d�O���[�v
�E������ʋ@�ւƎԂ̗�����}�邱�Ƃ����
�E�ǂ�Ȑl�ɂł���ʌ�������B�����̎����グ�Ă���
�E�d�Ԃ�o�X�Ȃnj�����ʋ@�ւ͊X�̍��Y
�E��������Q�҂ɂȂ�����A�ړ��l�b�g�������ɍs�����낤�Ǝv���� |
|
�u�`�@�Љ�I��҂Ɖ^��
�@
�\��Q�҉^���̗��j�\
�@�@�R�c���`����
�@�@ �i�Љ���@�l�`�i�t�����̉Ɓj |
�@ |
|
|
�������̊X�Â���^���t����
�����a48�N�悭�������ƎԂ����S���W��
�E���a48�N�A���s�ŎԂ����s���S���W��J���ꂽ�B���É��ł͂悭�����i���m���d�x��Q�҂̐������悭�����j���������A�Ԃ����̒��Ԃ��^�����n�߂Ă���B
�E�l��50�`60���̐��s�ŁA�w�ɂ͎Ԃ����ŗ��p�ł���g�C��������A�S�ݓX�ɂ͂���ԎԂ����ŗ��p�ł���g�C�����t���Ă����B200���s�s�̖��É��ɎԂ����ŗ��p�ł���g�C�����ǂ��ɂ��Ȃ������B
�E���̒��Ԃ��g���Ă����̂́u�������g��^���v���������A���ꂩ��͌����̌����g�����Ƃ��W��ō��ӂ���A�u�������g��^���v�ƂȂ����B
����Q�̊T�O�̊m��
�����ۏ�Q�ҔN�u���S�Q���ƕ����v
�E1981�N�ɍ��A�ŁA���ۏ�Q�ҔN�u���S�Q���ƕ����v���e�[�}�ɖړI�����c����A�^�����n�܂����B��Q�Ƃ͎Љ���������̂ŁA���Ȃ���������Q�҂����肾���Ă���Ƃ������ƁB
�E���ʂɂ����āA�ꕔ�̐l��r������Љ�͐Ƃ��Ďア�Љ�ƌ�����B�����A�w�Z�ɍs���Ă��A�ǂ��ɍs���Ă��A��Q�҂͂قƂ�nj�������Ȃ��B�{��w�Z�Ƃ������̂�����A��Q�҂������W�߂��B����ł̓C���e�O���[�g�ƌ����āA�������炪�E�߂��Ă���A���{�͒x��Ă���ƍ��A���犩�����Ă���B
���c�o�h���E��c�����̎��Ӗ�
���Ƃ���r�����ꂽ���ɑ��Ă̑R�ӎ����琶�܂ꂽ�B
�E�J�i�_�ŁA���Ƃ��W�܂����q�h��c�i���n�r���e�[�V�����E�C���^�[�i�V���i���j���������B�����҂ł��鎄�����ɂ���������^����悤�ɂƉ^�����������A���Ƃ́u�m�n�v�Ƌ��ۂ����B
�E��Q�ҕ����ł���A��Q�҂̐������Ƃ�������O�̂��Ƃł���B�m�I�Ȃ�m�I�A���o�Ȃ璮�o�A�Ԃ����Ȃ�Ԃ����̏�Q�҂̈ӌ������Ƃ���Ԃł���B�����҂̐����Ȃ����Ƃɑ���^�₪���܂ꂽ�B
�E�~�X�^�[�h�[�i�c�i�_�X�L���j��1981�N���疈�N�A��10�l�̏�Q�҂��{���t���ŃA�����J�̃o�[�N���[�𒆐S�Ƃ��Ď��������^���Ɉ�N�Ԍ��C�ɍs�������B���C����A���Ă����l���������{�̎��������^�����������B
�E�c�o�h�̃e�[�}�́u���玩�g�̐��v�B���E�̏�Q�҉^���́A�ǂ��炩�ƌ����A���ƑΓ����҂Ƃ����\�}�ɂȂ��Ă����B���{�̌��݂̏�Q�҉^�������l�ł���B
���Љ�I��҂Ɛ���
���n�����Љ�ł́A��������͂Ȃ��Ƒ��ɖw�Ljˑ����Ă����B
����Q�҂����N�����{�݂ɍs�������čs���Ă���l�́A�ق�̈ꈬ��̐l�B���ی��͉��͒n��Ŏx����Ƃ�����|�ł���B�s�������Ȃ��Ƃ���ɍs�������̂ł���A�{�݂͎��e���Ɠ����B
���l�����͉^�����Ă������ƂŁA��Q�ҁ��Љ�I��҂ł͂Ȃ��Ȃ����B��Q�͎Љ���肾�������A�Љ��Q����菜���Ă����Ă��ꂽ���Ƃ������B
�������o���Ȃ�����҂����ł�����̎ア��҂ƌ����Ȃ����B
�����ی��Ǝx����x�̈Ⴂ
���n��Ŏ�������������n��Ƃ������O�͓����B
�E�n��Љ�̑������������҂Ɛ��ƂƂł͂܂������Ⴄ�B���O�͓����ł������ł͉��ی��Ǝx����x�ł͑S���Ⴄ�B
�����ی��́A�O�ꂵ�����ƁE�Ƒ��哱�ɂ�鐧�x�B���ʂ͏d�ĂȏǏ�ɂȂ�����{�݁B
�����ꂩ��
�ЂƂ܂��u���̖����́A��Q�҂��j�Ƃ����A����҂₢�낢��Ȑl����������ŁA�m�[�}���C�[�[�V�����̊X�Â�������Ă������ƁB�F���s���Ƃ��āA��Q������Ȃ��Љ�������Ă������ƁB�{�݂���o�Ēn��Ŏx�����邵���݂������Ă������Ƃ������B����́A�n�[�g�ł͂Ȃ��A�����݂����邱�ƁB
|
|
����@���ی����x
�@�@�����錩����
�@�@
�i�����Љ���m���k���j |
�@ |
|
|
���Ȃ����ی������܂ꂽ�̂��i���ی��̖ړI�j
�����ی��̎�Ȏd�g��
�����ی��̌���Ɖۑ�
�E
��70���l�����T�[�r�X���Ă��Ȃ��B���܂��܂ȗ��p�}�����u���Z�b�g����Ă��邩��ł���B
�@���p�ҕ��S�P��
�A�v���F�����܂ł̔ώG�ȃv���Z�X�Ǝ���
�B�敪�x�����x�z�ݒ�
�C�{�ݓ�����V���[�g�X�e�C���̃T�[�r�X�ʕs����
�E�@�[�u����_��Ɉڍs���āA�s�����ւ�鑊�k�@�ւ�K�⊈�����k�����A�n��̌�������̑��������ȂNj@�\�ቺ�A���ʓI�ɖ����P�A�}�l�[�W���[�ɉ������Ă��銴�����Ȃ߂Ȃ��B
�� ���ی��̌�����
�E
�y�x�҂̑啝�ȑ����A�y�x�҂ɑ���T�[�r�X����Ԃ̉��P�Ɍq�����Ă��Ȃ��B
���\�h�d���^�V�X�e���ւ̓]��
�E
�ݑ�Ǝ{�݂̗��p�ҕ��S�̌������A���ی��ƔN�����t�̏d���̐���
���{���t�̌�����
�E
��l��炵����҂�F�m�Ǎ���҂̑����A�ݑ�x���̋����A����ҋs�҂ւ̑Ή��A��ÂƉ��̘A�g�B
���V���ȃT�[�r�X�̌n�̊m��
�E
�w�������Ǝ҂̑����Ȃǎ��̊m�ۂ��ۑ�A���p�҂ɂ��T�[�r�X�̑I����ʂ������̌���A�����̂��鎖��K�����[���A�P�A�}�l�W�����g�̌����E�����̊m��
���T�[�r�X�̎��̊m�ہE����
�E
�Ꮚ���҂ւ̔z���A�s�����̎������S�̌y���A����̐��������ی��^�c
�����S�̂�����E���x�^�c�̌�����
�E
�Z�݊��ꂽ�n��Ő����p�����\�ȁu���E������Ձv�̐����A�n��Đ��̂��߂̕⏕�����v
�����T�[�r�X��Ղ̂�����̌�����
|
�O���[�v���c
���c�O���[�v�ɒ����錩����A�d�O���[�v�ɎR�c���`����ɎQ�����Ă��������܂����B
|
|

|
|
|
|
�`�O���[�v
�E����̓����o�[�����ԂɈӌ����o���Ă����̂ł͂Ȃ��A�t���[�g�[�N�ŁA�|�C���g�ƂȂ鎖����tⳂɏ����Ăa���ɓ\���Ă����A��ł܂Ƃ߂Ă�����@�ŋc�_����
�E�����o�[���ʂ̊��z�Ƃ��āA�Ⴊ���҉^���̗��j��o�܂͂悭�����������A�Ⴊ���҂łȂ��������i�`�O���[�v�͏Ⴊ���҂����܂���j�ɉ����ł���̂��H�����]�܂�Ă���̂��H�Ƃ������Ƃ������Ȃ������A�Ƃ������Ƃ�������ꂽ
�����ƂɔC���Ă����Ηǂ��A�Ƃ����ӌ������邪�A��͂��X��l��l���A���ƂƓ����҂̗����̎��_�������Ƃ��K�v�Ȃ̂ł́H�Ƃ����ӌ��ɂ�������
�E�V�l�z�[���ɍs�������čs���Ă���l�͂��Ȃ��Ƃ����b�����������A�{���ɂ��Ȃ��̂��H�s�������Ȃ�悤�ȘV�l�z�[���͂Ȃ��̂��H
����삷�鑤�̈ӌ����肪���d����A�����⏰�����肪�d������Ă������A���ۂɘV�l�z�[���͕K�v�ŁA�N�̂��߂̎{�݂Ȃ̂��H�Ƃ����_���ǂ������Ă������A�Ƃ����v���Z�X���厖
���F�X�ȎM���K�v
�E���ی��ɂ��Ă��A���n�r�������j���[�ɓ���Ă���l�͉��x���������Ă���A�����łȂ��l�͏オ���Ă���A�Ƃ����X��������B
����상�j���[�ɂ��Ă��A����͐F�X�ȏ�Ԃ̐l�ɍ��킹���M���ł��Ă��邾�낤
���P�A�}�l�[�W������肭�R�[�f�B�l�[�g���Ă����K�v������
�E
�M�̗�Ƃ��āA�����悤�̓m�́u�S�W�J�����v��u�ڂ��ڂ������v�͂ǂ����낤�A�Ƃ����ӌ����o���B�ِ���ŏႪ���҂��܂��R�Ȍ𗬂��}��Ă���Ƃ����_�ŁA���z�̃R�~���j�e�B�ł͂Ȃ����낤���H
�c�O���[�v
�E�����搶�ɃO���[�v���c�ɉ�����Ă��������A���ی����e�[�}�Ɋ����Ȉӌ��������Ȃ���܂����B
�E�l�����y���ނ��Ƃ́A��Q�̂���Ȃ��A�N��ɊW�Ȃ��A�N�������ׂ������ł���Ƃ̂��Ƃɉ��ی���x����x�����邱�Ƃ��A���̓��c��ʂ��ċ��ʔF���ł��܂����B
�E���̒��ŁA�����̐��x���g���ɂ��������邽�߂̐��x���v�ɂ�萧�x���̂��ǂ�ǂ��Ȃ��Ă����Ƃ̈ӌ���A�g���K�v�Ȃ��l�܂ł������̐��x�����p���Ă��鎖��������Ƃ̈ӌ�������A���悢���x��d�g�݂Â���̓����Ɋ����܂����B
�E���c���e�̖͑����ւ̂܂Ƃ߂������A����l�ɂȂ��Ă��܂����B�悵�悵�B
�d�O���[�v
�@�����o�[���m�A��ۂɎc�������Ƃɂ��Ĉӌ����o�������A���̒�����u�Ⴊ���҂��n��ňꏏ�ɕ�炵�Ă������߂ɁA�K�v�Ȃ��́v�����c�̒��S�ƂȂ����B
�@�n��Z���Ƃ��Ĉꏏ�ɕ�炵�Ă������߂ɂ́A���݂��𗝉����������Ƃ���n�܂邪�A���̎Љ�ł͏Z�����m�̃l�b�g���[�N���@�\���炸�A����ɓ���̂Ȃ��ŏႪ���҂Ɗւ��@��Ȃ����ƂŌ݂��𗝉��������Ȃ��ƂȂ��Ă���B
�@����̂Ȃ��ňӌ����@��̏��Ȃ��Ⴊ���҂ɂ����A�����Ȕ����̂Ȃ��ɁA�Љ��ς��Ă������߂́u�L�[���[�h�v���܂܂�Ă��邱�Ƃ�����B�����q���ɋz���グ�A�Љ�S�̂̎d�g�݂Ƃ��Ă������Ƃ��K�v�ł���B
�@���ʂȏ�ł͂Ȃ��A����̂Ȃ��ŋC�y�ɗ������A���ł������������i�d�g�݁j�����A�l�Ɛl�Ƃ̌q�������ɑ�ɂ��Ă��������Ƃ������ƂɂȂ�܂����B
|
|