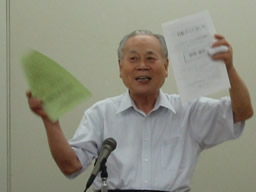�g�b�v�y�[�W���u�������m���@�l�ɂ₳�����X�Â���A���u����2005�N�x�@���炵���܂��ŕ�炷����5��
2005�N�x�@���炵���܂��ŕ�炷
|
���T���@�@�y�����z |
|
�����F8��27���i�y�j13:00�`17:00
���F���m���Љ����قR�K�{�����e�B�A�w�K��
��T��y�����z
�u�`�@��ʌ��\�Љ�Q���̂��߂Ɂ\
�@�@�X�c�D�ȁi���肽�܂��݁j����i���Ԋw����w�l���w���j
����@�s�����s���̂��߂�
�@�@�n��
���i�킽�Ȃׂ�����j����i�m�o�n�@�l�ړ��l�b�g�������j
���^����
�O���[�v���c |
|
�@����́u�m��E�w�ԁv�̂R��ځB��T��̃e�[�}�́u�����v�B�����̂�����Ƃ���Ɋւ��A�����̎���ۏႷ���ʂɂ��Ċw�т܂��B |
 |
|
�P�R�F�O�O�@�͂��܂�
|
�P�R�F�P�O�@�u�`�@��ʌ��\�Љ�Q���̂��߂Ɂ\
�@�@
�X�c�D�ȁi���肽�܂��݁j����i���Ԋw����w�l���w���j
�P�S�F�P�O�@����@�s�����s���̂��߂�
�@�@
�n��
���i�킽�Ȃׂ�����j����i�m�o�n�@�l�ړ��l�b�g�������j
�P�S�F�S�O�@���x�e���@
�P�S�F�T�O�@���^����
�P�T�F�Q�O�@�O���[�v���c
�@
�e�O���[�v�ŁA�����̍u�`�Ǝ�������ƂɃf�B�X�J�b�V�������܂��B
�P�U�F�S�O�@����̘A������ЂÂ�
�P�U�F�T�O�@�I��
|
�ʌ��\�Љ�Q���̂��߂Ɂ\
�@�@�X�c�D�Ȃ���i���Ԋw����w�l���w���j |
�@ |
|
|
���͂��߂�
�E�@�o���A�ɂ́A�����I�E���E�S���I�E���x�̂S������B�o���A����菜�����Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�g�����Ȃ��Ƃ����l�����Ŏ��g�ށB�Ⴆ�o�X�ł́A�Ᏸ�ɂ���ΒN�����g����B
�E
�������A'�N�ɂƂ��Ă�'�Ƃ����l�����ɂ͌��E������B�Ȃ�ׂ������̐l���g����悤�ɂƍl����B
�E
�C�����̖���Љ�̂�����A���x�̖��Ȃǂ�����̂ŁA�����I�ɍl���Ă����K�v������B
�E
��Q�҂⍂��҂͓��ʂȑ��݂Ȃ̂��B�N�ł��N�����ɂ�g���ɂ�����������B����s�̒����ł͔D�w����ȂǏZ�l��25������ʍ���҂Ƃ������ʂ��łĂ���B���t�{�̒����i����12�N�x�j�ł́A����҂ł́A�������A�ʉ@������Ƃ��ȂǁA�X�̂ǂ����ɕs�ւ������Ă���A75�Έȏ�ł͌�ʋ@�ւɊ����Ă���B
�E
�ʉ@�A�ʊw�A�������ȂǁA���퐶���ł͈ړ����Ƃ��Ȃ��B
�E ��Q�҂⍂��҂̌�ʌ��̕ۏ�����邱�Ƃ́A���ׂĂ̐l�̗��v�Ɍq�����Ă����B
������m�F
�E
�Ԏ��o�c�Ō�����ʋ@�ւ̘H���x�p�~�͔N�X���債�Ă���B������ʋ@�ւ��g�������Ă��A�g���Ȃ��������Ă���B�Ԃ��^�]�ł��Ȃ��l�A�Ԃɏ悹�Ă��炦�Ȃ��l�̐����ɉe�����Ă���B
�E
�����ԗ��p�̑���͒��S�s�X�n�ɂ����鏤�Ƌ@�\�̐��ނ������炵�Ă���B�����T���̋������Ԃōs���B�Ԃ��^�]�ł��Ȃ���Q�҂⍂��҂͎��c���ꂽ���݂ƂȂ�댯��������B
����Q�ҁE����҂̐l���ۏ�ƌ��
�E
�w��Q�҂̌����錾�x�́A��Q�҂��l�ԂƂ��Ă̑��������d����鐶�܂�Ȃ���̌�����L���邱�ƁA�\�Ȍ��莩��������悤�\�����ꂽ�{����鎑�i�����邱�Ƃ�搂��Ă���B
�E
���Ȍ���ł��邱�Ƃ���B
�E ��Q�ҁE����҂ɑ����ʌ��ۏ�́u�����̂܂��Â���v�q���鐶���������B
����ʌ��ۏ�ƌ�����ʌ��̖���
�E
�C�M���X�ł́A��Q�҂̑����������Ԃňړ����Ă��邪�A���̐l�ɉ^�]���Ă�����Ă���B���͂ňړ����Ă��Ȃ��B
�E
������ʂ̗��_�͎��͂ňړ��ł��邱�ƁB
�E
�Ԃ��g��Ȃ���������ʂ��g�������p�҂𑝂₷
��Q�҂̌�ʌ���ۏႷ�邱�ƂŁA������ʂ�N�ł����g���₷�����̂ɂ��A���̑��̐l�ɂƂ��Ă����v�������炷�B�Ᏸ����~���Ԃ̒Z�k���^�s���x�𑬂߉^�s�o��ߌ�
�E�X�y�V�����E�g�����X�|�[�g�̕K�v��
|
|
����@�s�����s���̂��߂�
�@�@�n�� ������i�m�o�n�@�l�ړ��l�b�g�������j
�u�ړ�����҂̂��߂́v�{�����e�B�A�ɂ�镟���L���^�� |
�@ |
|
|
�P�D
���^�N�s�ׂƌĂꂽ�{�����e�B�A�c�̂̌˘f��
3500�̎s���c�̂��ړ��T�[�r�X�����Ă���ƌ����Ă���B
������30�N�̗��j������u���ߏ��̕�炵���������v�Ƃ��Ē蒅���Ă���B
���{��30�N�ɂ킽��{�����e�B�A�̊�����ٔF���Ă����B
���H�^�H�^���@�͉^�����Ǝ҂̂��߂̖@���ł���B
���{�ɂ̓{�����e�B�A������F�m����@���������B
�Q�D
����18�N�R���̏d�_�w�����ԏI���܂łɈ��m�^�A�x�ǂɎ葱�����I���邱�ƁB
���m����59�̔�c�������c�̂łm�o�n�@�l�ړ��l�b�g���������B
���m���m���֓��t�{�ɃZ�_������\����v���i���N�V��19���ɐ��{���F�j
20�s�X���ʼn^�c���c����J�Â��m�o�n���̈ړ��T�[�r�X�̕K�v������������B
�n�������c�̂̐��E���t���āA���m�^�A�x�ǂɏ��F�\������B
�R�D
�ړ��l�b�g�������̉���c�̂̊�{�I�Ȏ��g�݂̎p��
���p�҂Ɉ��S�ƈ��S�����B
�K�C�h���C���������Ɏ��B
�ړ��T�[�r�X�̑Ώێ҂͈̔͂��K�C�h���C���̈ړ�����҂Ɍ��肷��B
���悻�^�N�V�[�^���̂P/�Q�ȉ��̗L���̑Ή��i�^���\�j���ł��邾�����ꂷ��B
�@�@���̐��x�̕�������_���͎葱�����I���Ă�����߂ĊW�Ȓ��ɒ���B
�S�D �K�C�h���C���ɂ��ړ�����҂̒�`�i��������240���S�D�i�Q�j�@���ɋL�ځj
�T�D
�K�C�h���C���̕�������_
���c���E�q�ǂ��͊܂܂�Ȃ��B����҂ł��P�Ƃňړ��ł���l�͊܂܂�Ȃ��A���B
|
|
���^����
�y����z������ʋ@�ւ̏[�����邱�Ƃ́A�ƂĂ��f���炵�����̂��Ǝv�����A���X�A�ǂ��Ȃ�Ȃ�����̂ł��傤���B�o�X��d�Ԃ�҂��Ă��Ċ�Ȃ��Ǝv�����Ƃ�����B������ʋ@�ւ͎Ԃ��Ȃ��̂Ŏd���Ȃ��g�����̂Ƃ����C���[�W�����������A�Ԃւ̌X�����q�ǂ��̂��납��A���ݕt���Ă��܂��Ă���̂ł��傤���B
�@
�@ |
|

|
|
�y�X�c����̓����z
�E�@�Ԃ������̂Ŏd���Ȃ��g�����̂Ǝv���Ă���ƁA���������P������Ƃ����悤�ɂ͏o�Ă��Ȃ��B������ʋ@�ւ͊X�̍��Y�ƍl����ƁA�����ƈႤ�������o�Ă���Ǝv���B
�E
�o�X��d�Ԃ̊�Ȃ��Ƃ���́A������Ǝw�E����B
�E
�o�X��d�Ԃ̒��́A�ړ������邽�߂̌����̋�Ԃł���Ƃ����ӎ��������Ȃ�������Ȃ��B
�y����z��ߏ��̕�炵�Ɣ��W�Ƃ����C�����͂킩��̂ł����A�{�����e�B�A�����Ă���l�����̐����̎����͐����ł��邾���̗Ƃ���̂ł��傤���B
�y�n������̓����z
�E
�����͂ł��Ȃ��B�����������x�ł���B
�E
�c��̐���A�o����ςl�������{�����e�B�A�̊����̘a�̒��ɓ����ė~�����B��������A�{�����e�B�A�̊����������ɂȂ�B��N�ސE���ĂR�N���炢�͔N���͂Ȃ��B�v�w��l�Ȃ�A�P�O���Q�O������ΐ����ł���B�{�����e�B�A�������Ȃ��炻�ꂮ�炢�̎�����������悤�ȃv���O�������l���Ă����K�v������B |
�O���[�v���c
���`�O���[�v�ɐX�c�D�Ȃ���A�a�O���[�v�ɓn�� ������ɎQ�����Ă��������܂����B
|
|

|
|
|
|
C�O���[�v
�w��ʌ��\�Љ�Q���̂��߂Ɂx�ɂ��ẮA�����o�[�̑������Ԃ𗘗p���Ă��邽�ߎ������������O���[�v���c�ɂ͎���Ȃ����������������B�e���̊��z�Ɩ��_���o���������B
�E�o�X�H���̔p�~
�E�w�܂ł̃A�N�Z�X���s�ւŗ��p�ł��Ȃ�
�E�������D�A���l�w�������A�Ԃ������p�҂͍����Ă��铙�B
�w�s�����s���̂��߂Ɂx�ɂ��ẮA�������������É����̑��݂��͂��߂Ēm���������o�[������������S�͏W�߂����A�����o�[�̐g�߂Ȗ��_���b��ɂȂ��Ă��܂����B
���O���[�v���c�̓��e�ɂ��ẮA�͑����ɂ܂Ƃ܂�܂����B
�|�X�g�C�b�g���g���A���h���̓C�}�C�`�Ȃ���A���Ƃ����\�ł���̍ق𐮂������ł́A����̉ۑ肪��N���A�ł��܂����B
�d�O���[�v
�����o�[�F����A�u��ʖ��Ƃ͐����̎��̖��v�Ƃ����Ƃ���ɐ[���S�������A�L���Ȑ����̎����̂��߂ɕK�v�Ƃ����u��ʁv�̂�����ɂ��ē��c���i�݂܂����B�u�N�ł��A�ǂ��ւł��v�Ƃ�����ʂ́u����ׂ��p�v�̎����̂��߂ɂ͗��p�҂̗���ɂ����Ďg�����Ƃ̂ł��������ʂ̐�������B�������A���̎����̂��ߍ����Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ́A�����Ƃm�o�n�A�{�����e�B�A���̍s���Ă���ڑ��T�[�r�X�ȂǂƂ̏Z�ݕ����ł��݂����K�v�Ƃ����j�[�Y�ɑ������Ă������ƁB
�@�N�����g���������ʂ̎����̂��߁A���������ɂł��邱�Ƃ́A�u���p����v�u�����o���v�u����������v���ƂƂ������ƂɂȂ�܂����B
|
|