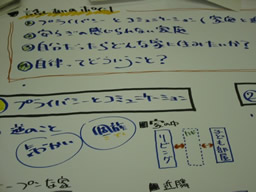トップページ>講座>愛知県 人にやさしい街づくり連続講座>2005年度 私らしくまちで暮らす>第4回
2005年度 私らしくまちで暮らす
|
第4回 【暮らす】 |
|
日時:8月20日(土)13:00〜17:00
会場:愛知県社会福祉会館3階ボランティア学習室
第4回【暮らす】
講義 すまいとくらし―安心して住み続けるために―
岡本祥浩さん(中京大学総合政策学部)
事例報告 地域居住
安井洋子さん(NPO法人もやい)
グループ討議 |
|
今回は「知る・学ぶ」の2回目。第4回〜第6回は講義と報告を聴きしっかり座学です。第4回のテーマは「暮らす」。地域で安心・安全に暮らすための住まいと暮らしについて考えます。 |
 |
|
13:00 はじまり
|
13:10 講義 すまいとくらし―安心して住み続けるために―
岡本祥浩さん(中京大学総合政策学部)
14:10 事例報告 地域居住
安井洋子さん(NPO法人もやい)
15:10 <休憩>
15:20 グループ討議
各グループで、今日の講義と事例報告をもとにディスカッションします。
16:40 次回の連絡&後片づけ
16:50 終了
|
講義 すまいとくらし―安心して住み続けるために―
岡本祥浩さん(中京大学総合政策学部) |
|
|
○住まいの要件
1)空間として適切な要件を備えていること
適切な広さ・設備等、プライバシーの確保とコミュニケーションの可能性
2)法律的に適切なこと
すべての人はこの地球上に居住する権利を有している
3)経済的に適切なこと
家計にとって無理のない負担の範囲で確保する
○居住者としての要件
1)自律していること
他者に(精神的に)依存せず、社会の構成員として生活することができる
問題が生じた場合、居住者として責任を持って判断し、行動できること
2)社会的に貢献していること
労働が可能な者は働いて賃金を得たり、税金を納めて社会に貢献したりする
そうでない者は、他の方法や手段あるいは社会とつながりを持つことによって自分の存在価値を実感することができること
3)ライフスタイルに適合していること
○すまいの現状と問題
・
日本のすまいの居住水準(広さ、設備、質)は低い
・ 経済的に余裕のない者は耐震性のない住宅に住まざるを得ない
・
諸外国と比較すると、日本人はすまいにやすらぎを感じていない
・ 近年、家庭内事故による死亡者数は交通事故死より多くなっている
・
社会的弱者に配慮されない住宅事情
○安心して住み続けるために
・ 何人も居住に関わる差別を受けず、社会的に排除されないこと
・
居住・都市などは自然生態系を尊重して創られること
・
生活条件(社会資本)の形成は当事者を中心として進めること
当事者は主体としてその認識を深め、その能力の向上に努めること、等。
|
|
事例報告 地域居住
安井洋子さん(NPO法人もやい) |
|
|
○「おらんがええわなぁ」というつぶやき
おったがええか、おらんがええか、どちらかと言われれば、おらんがええわなぁと、50才になったばかりの時に耳にした老人の呟きに、絶対に「おらないかん」でしょと。
日本では親は子どもを自立させることを目的に生きている。子どもが自立してしまうと、子どもの世話になる自分が残っているだけ。最後は介護されるようになり「おらんがええわなぁ」という気持ちになってしまう。でも、私はいつも私でありたい。自分が老いてこの人の歳になったときこんな言葉を口に出さなくても良い場を作ろうと思った。
○役所に相談
役所に相談すると、やるのはいいが自己責任でやるように、反対しないが、支援もできないと言われた。
○移送サービスから
最初、無償ボランティアで全てをやろうという意気込みだったが、それでは長く続けられないだろうということで、1回1,000円の有償サービスにした。
阿久比町では移動補助は月2回、つまり1日病院に行けるだけの支援しかない。他に出掛けたければタクシーを利用することになるが、細い道は敬遠され、乗り降りが遅いと嫌われる。
リスクが大きく、したくないと思っていた移送の仕事ではあったが依頼があり引き受けた。
○助成金の申請は積極的にする
以前は、よそから不用品が出ればとんで行ったが、今では助成金で必要なものを得るようにしている。助成金の申請書を書くことは自分たちの活動を振り返る勉強にもなり、申請が認められれば、自分たちの活動が認められたことと解釈している。この頃は、遠慮せず、必要なものを相手に言うことにしている。
色々なところに顔も出す、人の輪のつながりも大切。
○7年が経って
役所から言われた「10年続けられるか?」という投げかけに後3年となった。私たちの活動を役所もだんだんと気に掛けてくれるようになった。デイサービスでは、アクセサリーを作りみんなに喜んでもらっている。しめ縄作りもする。三河漫才など習い、文化伝承の場にもなっている。老人の知識、知恵も捨てたものではない。たくさんの色々な人の集まってくる場になった。これからは団塊の世代にどう参加してもらうか。今、セダン特区の移送サービスの申請書の準備に忙しくしている。
|
グループ討議
☆講座終了後、サポーターのみなさんにグループの様子を聞きました。
※Cグループに岡本祥浩さん、Dグループに安井洋子さんに参加していただきました。
|
|
|
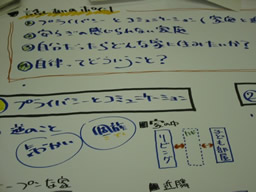 |
|
Aグループ
講義「すまいと暮らし」の関連で、グループメンバーから
1.プライバシーとコミュニケーション
2.安らぎの感じられない家庭とは
3.自分ならどんな家に住みたいのか
4.自律とは何?
という4つの討議テーマが出され、それについて各自持論を展開し、「暮らし」についてのさまざ
まな問題点を共有できたように思われた。
次に「事例報告―地域居住―」については、講師の「自分が何をしたいのか?」の問題提起にグループが反応し、それぞれ自分のしたいこと、日ごろ考えていることを中心に思いを披露した。 問題意識をより高めて講座に向かう意欲が感じられたグループ討議であった。 |
|
|
Cグループ
〇各自の講義の感想と質問(その都度岡本先生が答える)
〇岡本先生からの補足と助言
〇各自の生活する地域での生活や暮らしについて意見交換
・子供部屋、逆に親が高齢になった時部屋が無い
・新空港ができた事で、小牧空港周辺の地域環境が大幅に変わった事
・最近の行政の動向について(住民の立場と行政の立場で)
・障害のある人や高齢者に対する、借家や公営住宅の不備
・地域のコミュニケーション(祭りなど)の様子など
〇グループ討議から見えてきたもの
・コミュニケーションの重要性とプライバシーの問題
・自律と協調の結論に落ち着く
〇グループのメンバーが自覚した問題点
討議そのものは、全員が活発に発言し、意見交換もできるが、発表するために模造紙にまとめる段階での手法に大きなカベがある。
※岡本先生から、ポストイットの上手な使い方や、まとめ方について助言があり、今後の方向性を見出せたと思われる。
グループの記録は記録係の報告で集約していく方針です。
Dグループ
・ 講師の安井さんにグループ討議に加わっていただき、貴重な体験談やご意見を聞くことができました。
・ 始めてのグループ討議では、受講者それぞれが「地域で生きること」に対するご自身の考え方を披露してくれて、改めてみなしっかりとした考え方をお持ちだと認識できました。
・ 地域とどう関わっていくべきかとのテーマで話し合った結果、「いつもニコニコ、笑顔で」「熱いハートを持って」じっくりと時間をかけて付き合っていくことが必要だ、との結論に達しました。
Eグループ
・
地域で「暮らす」というテーマに関心は高く、グループ討議では一人ひとりが講義中のキーワードを自分の日常生活と照らし合わせての意見が多く出されました。
・
メンバーそれぞれの意見や地域で暮らすことへの想いを聞くことで、「考え方は一つではない」ということを感じ、視野を広げるためにも、自分の意見・考えを深めていくためにも人の意見を聞くことの大切さにあらためて気付きました。
|
|