提案・研究会
トップページ>提案・研究会>愛知のひとまちを良くしたいWS>第10回
第10回 まとめのワークショップの1回目
| ■とき:2003年11月29日(土) 第1部:1時30分~5時30分 第2部:午後6時~8時30分 ■ところ:あいちNPO交流プラザ(名古屋市中区三の丸3-2-1 東大手庁舎1階) ■参加人数:26名(うち要約筆記者5名) |
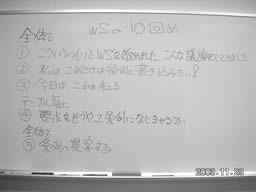 きょうのながれ |
 考えて、発言して、議論して・・・ |
 自己紹介しながら「これだけは条例に入れたい!」を発表 |
 「これだけは条例に入れたい」を書いています、ひとつに絞るのは難しい |
 ヘルパーさんが代筆しています |
 条例と照らし合わせながら・・・ |
 テーマ毎にグループで議論しつつまとめ |
 こういうことかなあ~ |
 そっ、そうなんだよ・・・ |
 ここれでいい? |
 グループのまとめを発表、きょうはパソコン要約筆記です |
 出された意見をグルーピング |
 きょうの作業のまとめです、みなさんお疲れさま |
|
第1部
1.こういうつもりでWSをはじめました
・これまでのワークショップのおさらいと、今回の進め方の説明
2.私はこれだけは条例に書き込みたい!-自己紹介をかねて主張する
森さん
・
事務局を含めて参加している。常に思っているのは、条例の見直し期間を条例にうたっていないので、定期的に見直すしくみをつくらないと、時代に流れに追いつかない。細かいことをいうときりがないので、大きな枠で話をさせていただいた。
・
時代の流れに合わせ設計基準を変えていくしくみ
・ 建設中または完成後に随時、建物の設計段階での障害者のチェックの義務付け
・
学校が災害時にも使われる重要施設なのでそれに見合った基準に
・ 条例制定の際、公募委員で決める
稲垣さん
・
既存の建物について何か基準をつくる(改修時だけでなく)
三好さん
・
情報が共有されない、伝わってこない、一部の人しか知らない。都市計画などもそうだが、もっと伝える努力を。
江尻さん
・企画スタートより利用者の参加をさせる。あえて「利用者」を強調
橋本さん
・
計画段階からの利用者の参加・参画、住民側も責任をもって参加する。ハードだけでなくソフトの面でも条例に入れていきたい
水野さん
・
知的障害のある人にもわかりやすいようなサインの統一化をしてほしい(トイレ、レジ、受付、切符・入場券の売り場等)。一昔前は「障害者は見ちゃだめ」ということを言われたが、もっとみてほしい。まちなかではデザインがバラバラでわかりづらいことが多い。
岡田さん
・
建物内の駐車場の高さ、リフトカーの高さは2m25cm、公共施設の多くは2m10cmと今の時代に合わない。
・
バリアフリーの中のバリア探し、やすらぎ会館は視覚障害者用の機能も不十分
佐藤さん
・
新しい住所に移り、知的障害者の授産施設のボランティアと学区内のコミュニティーセンターの管理人などをしている。交通機関のバリアフリー化が必要
岡本さん
・条例にあわせ整備基準をつくる(整備マニュアル)、ビジュアル化した整備基準(マニュアル化)
平山さん
・
愛知県重度障害者をよくする会。交通問題に取り組んでいる関係で、交通機関のバリアフリーを条例改正に盛り込んでいきたい。大きな駅や観光地の駅のエレベーター規格の寸法を大きくする、間口2m以上、奥行き1.5m以上。ノンステップバス
加藤さん
・
障害者パーキングの色指定、まわりから障害者用のスペースがわかるようにすれば、知多市で取り組んでいる。
・
公共施設(税金を使う建物)の面積制限なし、1㎡から
・
エレベーターの定員緩和規制、共同住宅、学校
小寺さん
・チェック機能を設ける
浅野さん
・古くなってきた公共施設の改修にあわせ、バリアフリー化を義務付け
西川さん
・
建築確認申請時にハード・ソフト両面を十分検討する。世の中全体でユニバーサルデザインという大枠の中で考えていく。自治体の考えとエンドユーザーの考えと両輪で。
鬼頭さん
・当事者参加のしくみをつくる
星野さん
・
不特定多数という概念を「みんな」にする。
・ あわせて「日常」に義務要求する。小規模施設、住宅、就業の場も。
・
主体者としての意見反映を保障する
・ 参加と学習支援、意思決定支援委員会、情報公開、年次報告
・
チェックの手法、手続きをきちんと、罰則も
○意見のまとめ
・不特定多数
・市町村計画
・委員会当事者参加
・情報
・既存の建物にも
・企画段階からの利用者参加
・チェック体制、建設中もちゃんとすること
・公共施設はすべて、学校は特に、交通機関のバリアフリー化
・サイン、トイレ、エレベーター、駐車場
・マニュアルをつくること
・条例を定期見直し
これ以外で
・
色(心理的な面も含め)、誘導ブロックの色など
・ 公共建物は全て確認申請が出るのでしょうか?
3.今日はこれを考える
■2で出た意見のうち、次の4つのテーマに分かれてディスカッションした
・
条例そのものへの参加、委員会当事者参加、市町村計画
・ 企画段階からの利用者参加、チェック機能
・
対象物-既存の施設、公共施設、学校は特に
・ 交通機関のバリアフリー化
■議論した結果
○条例そのものへの参加、委員会当事者参加、市町村計画
・
ひとまちメンテナンス委員会(維持保全・監視)、条例改正、公募型
・ 教育広報活動
・ (手続き)条例改正する
・
罰則規定を考える
→「人にやさしい街づくり推進委員会」を設置する(新たに4章)
市町村の義務
○企画段階からの利用者参加、チェック機能
・ 利用者が参加する
・
地域性、専門性・当事者アドバイス
・ 委員会、委員の設定
・ 行政の情報公開
・
チェック機能
意見交換
・公共施設についてはやれるが、小規模の民間施設についてどのように考えているか。
・官民を問わず公共に寄与するものとすべき。
・チェック機能をどこに設けるか。事業者責務は条例の4条で「業者は、その事業の用に供する施設を高齢者、障害者等を含むすべての県民が円滑に利用できるようにするとともに、県が実施する人にやさしい街づくりに関する施策に協力する責務を有する」と書いてある。一定規模の基準を設ければチェック機能も可能だろう。
・最も懸念されるのは個人病院。規模が小さくても取り組まねばならない。
・利用時間の長短も考慮
・個人病院、利用時間についていえば、用途によるのではないか。
○対象物-既存の施設、公共施設、学校は特に
・
基本は全ての施設→100㎡以下、50戸以下の共同住宅、事務所を全て、個人住宅にも
・ 公共の既存施設-○○年までに整備する、ランク付け表をつくる
・
民間の既存-最低限必要なもの(入口のスロープ、点字ブロック、トイレ)、小さい施設をどうするか
意見交換
・
住宅については土地で段差があるところが多く、そこまでは守りきれなさそう
・ 今後は造成からバリアフリーに配慮する
・
「望ましい」というスタイルをとってはどうか
・
個人のものである以上、個人住宅を条例に盛り込むのは難しい、共同住宅の中で何戸かはバリアフリー住宅にする規定をもうけたらどうか
・
個人住宅の中まで規定を設けるのは難しいが、アクセスするところはバリアフリーに。共同住宅では20戸くらいで規定を設け、公営住宅は全てバリアフリーにした方がいい。アクセスについては無理な造成をさせないという意味もある。
・
障害を持つまでは和風住宅(必然的に段差がある)を希望していたが、障害を持ったら和風の間取りでは間口が狭く、車いすが通れる80cmもとれない。120cmは取れるように。
・
全て対照したらどうか。事務所、工場とも対象にすべき。
・
公共の既存施設については建替え計画をつくるべき。民間の既存施設については、整備義務要求、計画も意見反映、既存でも新設と同様の報告、調査、規定適用。
・
既存施設について義務化するのは難しい。地域から声が出たら立ち入りする規定を設けたらどうか。
・
マンション住民の立場から、マンション建替えの際にバリアフリーのアドバイスをいただければ。
・
既存の施設も義務化した方がいいし、民間でも大規模な建物は義務化したほうがいい。小規模な建物は努力規定にしたら。
・
個人住宅では難しいが、公共施設で位置づければ、規格物でバリアフリーに対応するものが市場に出回る。
○交通機関のバリアフリー化
・
高架駅、地下駅のエレベーターの設置義務化、設置の期限を決める
・
鉄道駅で始発から終電まで1つのルートはバリアフリーに(例えばエレベーターの営業時間)
・ ノンステップバスの義務化、設置の期限を決める
・
案内表示の統一化、わかりやすく、色をはっきり
・
駅に関する情報を一本化、例えばJR・名鉄・地下鉄の工事情報、エレベーターの定期点検日の周知
→時間切れのため第2部へ持ち越し
第2部
2.私はこれだけは条例に書き込みたい!PART2
森さん
・ハードでできないものはソフトで対応しよう
山川さん
・
常設委員会の設置を条例の中でうたう
曽田さん
・ 人材養成をする。例えばアドバイザー、ボランティア、ガイドヘルパー。
・
学校の教育、総合学習の一環で。学校そのものも当然バリアフリーに。
玉腰さん
・
施設の入口に情報PCの設置
稲垣さん
・ 点字ブロックの統一化
小寺さん
・
人的対応、このニーズに合わせた配慮を義務付ける
平山さん
・視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者の情報保障、(音声案内、点字案内、文字案内、サイン案内)
佐藤さん
・
第11条の不特定をカット
浅野さん
・
高架駅、地下駅でのエレベーター、エスカレーターの設置義務化、営業時間を始発から終電まで義務化
西川さん
・
情報の共有化により市民参加
三好さん
・ 情報を知ってもらうための義務化
岡田さん
・
施主より設計者との話し合いの場を
・ 図面寸法入りでわかりやすく
江尻さん
・
建物に対して利用者に対する義務化を盛り込めたら
橋本さん
・
学校のバリアフリー化、障害を持った人に対して居場所として、トワイライトスクール等学校だけで使うのはもったいない
3.今日はこれを考えるPART2
・交通
・学校
・人材、ソフト的な話
・情報
○学校
・ エレベーターがない
・
当事者が学校にいることが大事、人にやさしいまちづくりを体験できる場
・
空き教室の利用、今は学校長の判断となるので責任問題、条例に位置づけたほうが
・ 車意志で利用できると居て、エレベーター設置、スロープ
・
避難先の充実、体育館の充実
・ 小中学校だけでなく大学も含めたい
・
12/5に東区講堂にて愛知教育大付属中学の車いす体験の発表会がある
意見交換
・
当事者が学校にいることについて、障害者が学校に行けないことがわからない。
・
学校は学生が生活をする場なので、バリアフリー化するべき。そうなれば当事者の選択性も増える。
・
先ほど公共、民間も含めて新設、既存の施設について整備計画をつくることを提案に入れたので、公立の学校、私立の学校もバリアフリー化を義務付けることになる。まずは、父母も学校に行く、災害時に拠点施設になる、という点から訴えていこう。
○ソフト
・ 話を聞くだけではダメ、連続講座、実習
・
人材育成、どんな人を要請するかにより方法は変化
・ 互いに認め合うことができるような教育、計画を立てる人、設計をする人重要
・
市民意識の向上、まず学校の教育が必要
・ ひとまち委員は公募であるが、例えば人街アドバイザー=講座の卒業生を優先させる等
・
ハードで対応しきれない場合は人手対応する
・ スーパー、空港など単独で移動が困難な場合、案内所まで誘導する
・
リストラしない人員の確保
意見交換
・ 人材育成を条例にきちんと位置づけたらどうか。今も連続講座や地域セミナーをしているが。
・
福祉系の人たちも人にやさしいまちづくりに巻き込みたい。
・ 施設での人的対応も
○情報
・
規則の16条では視覚障害者の利用が多いところに限定しているが、聴覚障害、知的障害、子ども、外国人など限定しないようにする。
・
案内表示に限定せず、案内と書いて多様な対応をする。
・ 音声、文字、サインを3点セットで義務付け。
・
サインの統一化を進める。マニュアル化。
・ 緊急時のサイン、お知らせ。
意見交換
・ わかりやすい案内(音声情報、サインなど)
・
非難時の誘導
○交通
・ 公共交通施設だけでなく、乗り物を対象にしたい
・
駅のエレベーター設置について、5000人以上の駅、5m以上の高低差という規定をはずし、高架駅、地下駅についてはエレベーター設置を義務化。
・
ホームドアの義務化
・ 車両内での文字情報、音声情報の義務化
意見交換
・
高架駅は電車の規定で5m以上はある。高架駅としたときに、総合駅などでホームが複数あるところが対象から外れる場合がある。問題は地下駅。5m以上の高低差と地下駅という規定があればよい。
・
エレベーターと同様にトイレも議論。改札の中は鉄道事業者でトイレを設置しなければならないが、改札の外をどうするか。
・
交通バリアフリー関係をどこまで増やすか。乗り物まで対象を広げたらどうか。
・ 乗降場における転落防止策は入れておいたほうがいい。
○その他
・ 工事中のバリアフリーの保障
・ マニュアルづくり
・
条例を定期的に見直すしくみ
・ トイレのつくりかた(子ども用にも)、エレベーターのかごの大きさの規定
4.条例へ提案する
○総括
・ 人にやさしい街づくり委員会を設ける
・
市町村の責務を負わせること
・ 計画策定では、委員会を設けること
・ 計画策定にあたっては利用者の意見を聞くこと
・
人材育成規定を設けること
・
対象施設を広げる-不特定多数、100㎡以下の規定ははずす、バリアフリーは個人の住宅については努力義務で公共施設は義務化する
・ 乗り物も規定に
・
駅などでの5000人以上、5m以上の高低差の規定をはずす
・ 多様な情報提供をわかりやすくするべき
・ サインの統一化
・
国、県、市町村の施設については計画を立てる、既存施設も改修計画を、利用者の参加を
・ わかりやすいマニュアル
・
エレベーターの規格の統一、トイレの大きさ
・ 条例について一定期間で見直す規定を入れる
(記録:浅野健、小寺岸子)
バナースペース
特定非営利活動法人
ひとにやさしいまちづくり
ネットワーク・東海
〒463-0096
名古屋市守山区森宮町100番地
TEL/FAX 052-792-1156
Eメール hitomachiあっとまーくnpo-jp.net
(迷惑メール対策のため@をあっとまーくに変えてあります)
